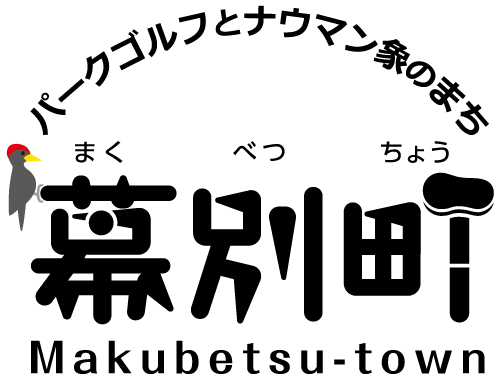国民健康保険制度
わが国は、すべての国民が何らかの医療保険制度に加入する国民皆保険制となっています。したがって、職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
国保は加入者(被保険者)の支払う保険税と国や都道府県の補助金などをもとに、市町村や国保組合(保険者)によって運営されています。
国保の加入・脱退手続き
次のようなときには14日以内に手続きが必要になります。
- 加入するとき
- 幕別町に転入したとき。
- 退職などで職場の健康保険をやめたとき。
- 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき。
- 子どもが生まれたとき。
- 生活保護を受けなくなったとき。
- 脱退するとき
- 町外に転出するとき。
- 就職などで職場の健康保険に加入したとき。
- 職場の健康保険の被扶養者になったとき。
- 亡くなったとき。
- 生活保護を受け始めたとき。
※75歳により後期高齢者医療制度への移行に伴う国保の資格喪失については、手続きの必要はありません。
- 手続きが遅れた場合
- 加入(取得)の手続きが遅れると資格が発生した時点までさかのぼって保険税を納めなければなりません。
- 脱退(喪失)の手続きが遅れると国保の資格がなくなったあとに国保で医療を受けた場合に、国保が負担した医療費を返還しなければなりません。
被保険者証の取り扱い
- 被保険者証を受け取ったときは、住所や氏名・生年月日などの内容をよく確認してください。
- 医療を受けるときには必ず提示してください。 (月の途中で健康保険が変わったときには、かかりつけ医でも必ず連絡してください。)
- 被保険者証の貸し借りはできません。また、コピーしたものや有効期限を過ぎたものは使えません。
- 住所変更や結婚など内容に変更があった場合は、窓口で手続きをしてください。
- 国保を脱退するときは、必ず被保険者証をお返しください。
※ 被保険者証の再交付について…国保の被保険者証を紛失・破損・汚損したときは、申請により再交付しますので窓口で手続きをしてください。
国保の給付
- 療養の給付
国保に加入している方が医療を受けられるときには、かかった費用の一部を窓口で負担(一部負担金)し、残りを国保が負担することになります。この国保の負担を保険給付といいます。「被保険者証」を医療機関に提示して、窓口で支払う一部負担金は次のとおりです。- 窓口での負担割合
窓口での負担割合 年齢区分 負担割合 義務教育就学前 2割 義務教育就学後~70歳未満 ※1 3割 70歳~74歳 (高齢受給者) ※2 現役並み所得者 3割 一般・低所得者 2割 ※1 「70歳未満」は、70歳に達した月の末日までの期間を含みます。
※2 75歳からは後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。 - 一部負担金の減免
特別な事由に該当し、生活が困難になったと認められる場合は、一部負担金の免除・減額・徴収猶予をすることができますので、窓口で手続きをしてください。
- 窓口での負担割合
減免制度とは
過去1年以内に、特別な事由のいずれかに該当し、一時的に著しく生活が困難になったと認められるときは、一部負担金の免除・減額・徴収猶予の申請をすることができます。
一部負担金とは
保険医療機関(医科・歯科)および保険薬局で支払う医療費の自己負担額。
特別な事由とは
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記(1)~(3)の事由に類する事由が生じたとき
減免の区分
| 区分 | 条件・内容 |
|---|---|
| 免除 | 世帯主と被保険者の収入合計(必要経費控除後)が、生活保護基準額以下の場合、一部負担金を免除します。 |
| 減額 | 世帯主と被保険者の収入合計(必要経費控除後)が、生活保護基準額を超え、かつ生活保護基準額の1.2倍以下の場合、一部負担金の2分の1を減額します。 |
| 徴収猶予 | 免除・減額以外で町長が必要と認めた場合で、猶予する期間内に一部負担金を確実に納付できる見込があるときに、6カ月以内で徴収を猶予します。 |
減免の条件
世帯主と被保険者の預貯金の合計額が、生活保護基準の3カ月以下であること。
※申請後、現地調査などにより確認をすることがあります。
※国保税の滞納の有無は問いません。
※一度、減免の適用を受けた人は、同一の事由による再度の申請は認められません。
※特別な事由に該当しない恒常的な低所得を理由とする申請は対象外です。
減免の期間
申請した月から連続3カ月以内を基本とします。
※必要と認められる場合、延長することは可能です。
※毎月の状況を確認し、必要と認められる場合のみ減免します。
申請手続き
※緊急な場合を除き、事前に申請書と必要な書類を提出してください。
※承認を受けた場合は、保険医療機関に被保険者証とともに証明書を提示してください。
- 手続きに必要なもの
- 収入状況の証明に必要な書類(次に掲げる書類のうち必要な書類)
ア 収入状況申告書
イ 給与証明書
ウ 事業収入申告書
エ 収入(無収入)申告書
オ 同意書
カ 雇用保険受給者証
キ 預貯金通帳等預貯金の残高確認ができる書類
ク その他収入状況の証明に必要な書類 - 傷病の状況の証明に必要な書類
ア 医師の意見書 - 資産の損害状況の証明に必要な書類(次に掲げる書類のうち必要な書類)
ア リ災証明書
イ 盗難証明書
ウ その他資産の損害状況の証明に必要な書類
- 収入状況の証明に必要な書類(次に掲げる書類のうち必要な書類)
- 療養費の支給
- 後で払い戻しが受けられるとき
次のようなときは、かかった費用の全額を窓口でいったん負担していただきますが、領収書等をお持ちになって申請していただければ、療養費として一部負担金を除いた額をお支払いいたします。- 被保険者証を持たずに医療を受け、医療費の全額を支払われた場合
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
- 骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき(ただし、柔道整復師が国保を取り扱っている場合は、一部負担金のお支払いで済みます)
- 医師が治療上必要と認めた、あんま・はり・きゅう・マッサージなどの施術料
- 輸血したときの生血代
- 海外渡航中に国外で診療を受けたときの費用
※申請にあたり、領収書のほか、それぞれ証明書等が必要となります。
- 国保の給付の対象とならないもの
病気やケガと認められないものや、他の保険が適用されるものは、国保の被保険者証で医療を受けられなかったり、保険給付が制限される場合があります。- 病気やケガと認められないもの
- 健康診断、集団検診、予防接種、人間ドックなど
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正、美容整形
- 日常に支障のない、軽度の「わきが」「しみ」などの治療
- 給付が制限されるもの
- けんかや泥酔などによるケガや病気
- 犯罪行為や、故意によるケガや病気
- 医師や国保からの指示に従わなかったとき
- 労災が適用されるもの
- 仕事上のケガや通勤時のケガなど
- 病気やケガと認められないもの
- 後で払い戻しが受けられるとき
高齢受給者(70歳以上の方の医療)
国保の被保険者で、70歳以上の方(後期高齢者医療制度に移行している方を除く)は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から、『高齢受給者』となり、医療を受けられる際の負担割合が2割、世帯の状況や所得などによっては3割となります。
該当される方には、70歳になられた月の末日までに「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(被保険者証に一部負担金の割合を印字したもの)をお送りしますので、医療機関の窓口に提示してください。
※1日生まれの方は誕生日の月から該当になりますので、誕生日までにお送りします。
- 5月2日が誕生日の方 ~ 6月から該当のため、5月末日までに証が届きます。
- 5月1日が誕生日の方 ~ 5月から該当のため、4月末日までに証が届きます。
なお、毎年7月には当該年度の住民税の課税所得により、8月以降の1年間の負担割合を判定し、新たな証をお送りします。(受給者証は7月末が有効期限になっています。)社会保険や共済組合等の被保険者(被扶養者)の方は、ご加入の社会保険事務所等にお問い合わせください。
区分について
世帯の所得状況等により、次の6つの区分が定められており、区分に応じて、医療費の自己負担限度額の適用(高額療養費について参照)や、入院時の食事代の減額の適用など(国保の給付について参照)を受けることができます。
- 現役並み所得者3 各種控除後の課税所得が690万円以上の70歳以上の方、およびその方と同じ世帯の70歳以上の方。
- 現役並み所得者2 各種控除後の課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上の方、およびその方と同じ世帯の70歳以上の方。
- 現役並み所得者1 各種控除後の課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上の方、およびその方と同じ世帯の70歳以上の方。
- 一般 住民税課税世帯で「現役並み所得者1・2・3」以外の方。
- 区分1 世帯主と世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各種所得が0である方。(年金の場合は収入が80万円以下。その他の場合は収入金額から必要経費・控除を差し引いた額が0であること。)
- 区分2 世帯主と世帯全員が住民税非課税の方。
※現役並み所得者1・2・3に当てはまる方のうち、その世帯の該当者の年収が520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合は申請により2割(特例措置適用の方は1割)負担となります。(該当される方には別途ご案内いたします。)
退職者医療制度
会社などを退職したことにより、国保の被保険者になる方で、次の要件を満たす場合は、65歳に達した月の末日までの間、国保の退職者医療医療制度の適用を受けることとなります。
※現在、退職者医療制度は廃止となっており、これに伴い平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までに退職者医療制度の該当となっている方は65歳到達まで引き続き適用となります。
- 退職者医療制度の要件
- 国保に加入している方
- 65歳未満の方
- 厚生年金や共済組合などの老齢(退職)年金受給者で、その加入期間が20年以上あるか、40歳以上の加入期間が10年以上ある方(国民年金の期間は含みません)と、その被扶養者
※被扶養者とは、退職被保険者本人の配偶者(内縁関係を含む)および3親等以内の親族で、本人と同一世帯に属し、本人により生計を維持されていて、年間収入が130万円未満の方。
- 届出
年金の受給権が発生した日、または年金を受給している方が国保に加入された日から退職者医療制度の資格を取得しますので、該当される方は窓口で手続きを行ってください。 - 必要書類年金証書(加入期間の確認できるもの)
国保に加入されている方は被保険者証(新たな退職被保険者証と交換いたします。) - 窓口での負担割合
窓口での負担割合 年齢区分 退職被保険者本人 退職被扶養者
(配偶者・被扶養者)義務教育就学前 - 2割 義務教育就学後~65歳未満 3割 3割
※1 「65歳未満」は、65歳に達した月の末日までの期間を含みます。
高額療養費
国保に加入している方(または世帯)が同一の月に負担した医療費が一定の基準額を超えた場合は、高額療養費として払戻しを受けることができます。
基準額は、年齢や支給回数などにより異なりますので、以下を参考にしてください。
- 70歳未満の方
同じ世帯の中で国保に加入している方が、医療機関ごと(入院・外来は別。総合病院などでは診療科ごと)に21,000円以上負担した場合に、負担した医療費を世帯全体で合計し、表1に該当する区分の限度額を超えた部分が対象になります。
表 1※1 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額です。令和3年8月以降は、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。70歳未満の方 区分 所得要件 ※1 3回目まで ※2 4回目から ※2 ア 旧ただし書所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 イ 旧ただし書所得600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円 ウ 旧ただし書所得210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 エ 旧ただし書所得210万円以下 57,600円 44,400円 オ 住民税非課税 35,400円 24,600円
※2 過去12ヵ月以内に高額療養費の該当になった回数を表します。 - 70歳以上の方
外来分の限度額と、入院分および世帯合算時の限度額がそれぞれ定められており、表2に該当する区分の限度額を超えた部分が対象になります。
表 2※区分1・2については「高齢受給者(70歳以上の方の医療)5、6」を参照してください。70歳以上の方 区分 外来(個人) 入院・世帯合算 現役並み所得者3
(負担割合が3割の方)- 252,600円+(医療費-842,000円)かける1%) 4回目以降は140,100円 現役並み所得者2
(負担割合が3割の方)- 167,400円+(医療費-558,000円)かける1%) 4回目以降は93,000円 現役並み所得者1
(負担割合が3割の方)- 80,100円+(医療費-267,000円)かける1%) 4回目以降は44,400円 一般 18,000円(年額上限144,000円) 57,600円 4回目以降は44,400円 区分2 8,000円 24,600円 区分1 8,000円 15,000円 - 70歳未満の方と70歳以上の方との合算
同じ世帯の中に70歳未満の方と70歳以上の方がいる場合は、それぞれを別に計算した後に合計し、表1の限度額を適用します。 - 計算する時の注意点
- 毎月1日から月末までの、1ヵ月ごとの診療について計算します。
- 病院・診療所・薬局ごとに計算します。同時に2ヵ所以上の医療機関で診療を受けている場合は、別々に計算します。(1つの医療機関の診療でも歯科は別計算になります。)
- 同じ病院・診療所でも通院(外来)と入院は別計算になります。
- 総合病院の場合は、診療科ごとに別々に計算します。ただし、入院されている方が別の科の診療を受ける場合は合算します。
- 差額ベッド代や食事療養費は支給の対象外です。
- 限度額適用認定
入院・手術などで高額な医療費の負担が必要となる場合、あらかじめ限度額適用認定証を医療機関に提示することにより、自己負担額が限度額までとなり窓口での負担を軽減することができます。申請した月の初日からの適用となりますので、適用を受けようとする月の末日までに申請により限度額適用認定証の交付を受けて医療機関へ提示してください。
※区分が70歳未満の住民税非課税世帯、70歳以上の区分1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」となり、入院時の食事代の減額にかかる認定証も兼ねています。
※区分が70歳以上の現役並み所得者3、一般の方は、「被保険者証」を掲示することにより限度額の適用を受けられますので手続きの必要はありません。
手続きに必要なもの- 被保険者証
- 特定疾病の療養
長期にわたっての治療が必要となる、「人工透析が必要な慢性腎不全」「血友病」「抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(エイズ)」の場合は、ひとつの医療機関(入院と外来は別)ごとに一ヶ月の自己負担限度額が10,000円(人工透析が必要な慢性腎不全の方で上位所得者は20,000円)になります。
高額医療・高額介護合算療養費
同一世帯の被保険者において、国保と介護保険の自己負担の両方がある場合は、1年間(8月~翌年7月)のこれらの自己負担の合算額の上限(自己負担限度額)を設け、負担を軽減します。
| 区分 | 国保+介護保険 (70歳~74歳までの方) |
|---|---|
| 現役並み所得者3 | 2,120,000円/年 |
| 現役並み所得者2 | 1,410,000円/年 |
| 現役並み所得者1 | 670,000円/年 |
| 一般 | 560,000円/年 |
| 区分2 | 310,000円/年 |
| 区分1 | 190,000円/年 |
| 区分 | 国保+介護保険 (70歳未満の方) |
|---|---|
| 旧ただし書所得901万円超 | 2,120,000円/年 |
| 旧ただし書所得600万円超~901万円以下 | 1,410,000円/年 |
| 旧ただし書所得210万円超~600万円以下 | 670,000円/年 |
| 旧ただし書所得210万円以下 | 600,000円/年 |
| 住民税非課税世帯 | 340,000円/年 |
※70歳~74歳までの方の区分については「高齢受給者(70歳以上の方の医療)」を参照してください。
※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
※医療保険または介護保険いずれかの自己負担額が「0」の場合、対象となりません。
※自己負担の合算額から自己負担限度額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えない場合は対象となりません。
出産育児一時金の支給
国保の被保険者である方が出産したときには、出産育児一時金をお支払いいたします。(出産には、妊娠85日以上の死産・流産を含みます。)
なお、勤務先の健康保険(社会保険、共済組合等)に1年以上、本人として加入していた方が、退職して国保に加入後6ヶ月以内に出産した場合は、国保に加入される前の健康保険から支給されるため、国保からは支給されません。ご加入されていた健康保険にお問い合わせください。
| 分娩日 | 支給額 |
|---|---|
| 令和5年4月1日から | 488,000円(産科医療補償制度加入医療機関等での出産の場合は500,000円) |
※産科医療補償制度とは、分娩における医療事故により赤ちゃんが脳性麻痺となった場合、そのご家族に対して経済的補償を行う制度です。詳しくは、産科医療補償制度(公益財団法人 日本医療機能評価機構)のホームページ(外部リンク)へ
- 手続きに必要なもの
- 出産した方の被保険者証
- 振込先の口座番号のわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振込用の【店名、預金種目、口座番号】の記載された通帳をお持ちください。)
- 出産の事実を確認することができる証明書
- 死産・流産の場合は、医師の証明書
- 産科医療補償制度加入機関の証明がある領収書
- 医療機関等との「直接支払制度を利用するか否か」の合意文書
- 出産育児一時金の直接支払制度について
出産費用にかかる経済的負担の軽減を図るため、国保が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うものです。手続きについては、医療機関等において被保険者等が直接支払いの申請および受け取りについての代理契約を結んでいただくことで直接支払制度が適用となり、出産費用として事前に多額の現金を準備する必要がなくなります。
※出産費用が出産育児一時金支給額未満の場合は、差額が国保から被保険者等に支給され、また、出産育児一時金支給額を超える場合は、超えた額が医療機関等の窓口で被保険者等に請求されます。
※この直接支払制度を希望しない場合は、従来どおり出産後に出産育児一時金を国保に請求することができます。(ただし、出産費用を医療機関等にいったんご自身で支払うこととなります。)
葬祭費の支給
国保の被保険者が亡くなったときには、葬祭を行われた方に対し、葬祭費として30,000円をお支払いいたします。
- 手続きに必要なもの
- 亡くなった方の被保険者証
- 亡くなったことを確認することができる証明書
交通事故にあったときなどは(第三者行為)
交通事故にあったときや、他人の犬に噛まれたなど、第三者から傷害を受けた場合でも、国保の被保険者証を使って医療を受けることができます。
ただし、かかった治療費のうち、国保から医療機関へ支払った費用については、後ほど国保から相手方(加害者)に請求することとなりますので、必ず届け出をされるようお願いします。
- 届出に必要なもの
- 被保険者証
- 事故証明書
上記のほか、相手方の氏名や連絡先、自動車事故であれば自賠責保険や任意保険の加入状況などを必要に応じて確認いたします。
※注意 相手方との間に示談が成立してしまうと、示談の内容が優先され、国保から相手方に請求できない場合があります。治療が長期化する場合もありますので、示談は慎重に行いましょう。示談の前には国保に必ずご連絡ください。