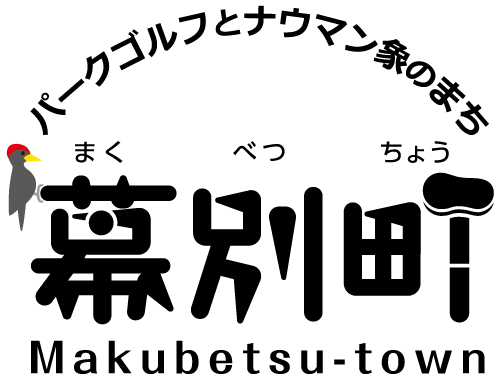妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
子ども・子育て支援法等の改正に基づき、従来の「出産・子育て応援給付金」に代わり、「妊婦のための支援給付」及び「妊婦等包括相談支援事業」が法定事業として新設され、令和7年4月から幕別町でも実施します。
(出産・子育て応援給付金事業については、こちらをご確認ください。)
事業概要
令和7年4月から、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法の「妊婦のための支援給付事業」と児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業」を効果的に組み合わせて、妊婦などの身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。
1.妊婦等包括相談支援
全ての妊婦及び子育て世帯を対象に、妊娠届出(母子健康手帳交付)時、妊娠8か月頃、出生後の新生児訪問時に、保健師などが出産・育児の見通しを立てるための面談を行います。
なお、妊娠届出時または出生後の新生児訪問時の面談と併せて、妊娠支援給付金について制度案内を行います。
2.妊婦のための支援給付金
給付対象者
幕別町に住民票のある妊婦の方
(注)産科医療機関で医師などによる胎児心拍の確認が必要です。
支給額
給付金の支給額は、次のとおりです。
1.妊婦であることの認定後 5万円
2.胎児の数の届け出後 胎児の数一人につき5万円
申請方法
申請方法については、次のとおりです。
1.妊婦であることの認定
妊娠届出時に制度案内を行いますので、案内に沿って申請してください。
妊婦支援給付金申請書(1回目) (656.1KB)(妊婦であることの認定申請)
2.胎児の数の届け出
新生児訪問の時に制度案内を行いますので、案内に沿って届け出してください。
妊婦支援給付金申請書(2回目) (23.4KB)(胎児の数の届け出)
申請期限(時効)
申請期限方法については、次のとおりです。
1.妊婦であることの認定申請
産科医療機関の医師等が胎児心拍の確認をした日から2年後の前日(注)
(注) 産科医療機関で胎児心拍の確認をした日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日を起算日とします。
2.胎児の数の届け出
出産予定日8週間前の日から2年後の前日
流産・死産・人工妊娠中絶をされた人へ
流産・死産・人工妊娠中絶となった場合でも支給対象となります。
詳しくは、こども課こども支援係にお問い合わせください。
妊婦のための支援給付事業は、出産・子育て応援給付金事業が法定事業化したものです。
このため、「妊婦支援給付金」と「出産・子育て応援給付金」を重複して受給することはできません。
なお、出産応援給付金のみ受給し、令和7年4月1日以降にこどもが出生する場合は、妊娠支援給付の認定申請並びに胎児の数の届け出をすることで、胎児の数一人につき5万円を受給することができます。
町外から本町へ転入した場合について
妊婦支援給付金は、同一の妊婦を原因として、重複受給することはできません。
なお、転入前の市町村で給付金を受給していない場合は、本町に妊娠支援給付の認定申請並びに胎児の数の届け出をすることで、給付金を受給できます。
本町から町外へ転出する場合について
認定後、本町から町外へ転出した場合は認定が取り消されます。
このため、本町で未支給の給付がある場合は、転出先の市町村において認定申請を行ってください。