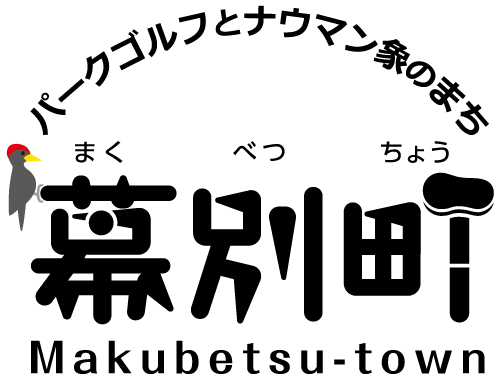サービス利用の自己負担と負担軽減
平成12年4月に介護保険制度が開始以来、サービスを利用したときの利用者負担は、所得にかかわらず、サービスにかかった費用の1割とされていました。
しかし、平成27年8月サービス分から、団塊の世代の方が75歳以上となる2025年(令和7年)以降にも持続可能な制度とするため、国全体で制度の見直しが行われ、65歳以上の方のうち、一定以上の所得がある方には、サービスにかかった費用の2割を負担していただくことになりました。
さらに、平成30年8月サービス分からは、65歳以上の方のうち、とくに所得の高い方には費用の3割を負担していただくことになっています。
利用者負担割合の判定基準
| 3割 | (1)(2)を両方満たす方
|
|---|---|
| 2割 | 3割に当てはまらない方で、次の(1)(2)を両方満たす方 (1)本人の合計所得が160万円以上である (2)同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が
|
| 1割 |
|
※第2号被保険者、市町村民税非課税の方、生活保護受給者の方は上記にかかわらず1割負担です。
※「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、事業収入に係る必要経費などを控除した後で、基礎控除や人的控除をする前の所得金額をいいます。また、譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算します。
※「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から、年金の雑所得金額を除いた所得金額をいいます。
負担割合証を発行します
要介護(要支援)認定を受けている方全員に、上記の利用者負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を発行しています。
負担割合証は毎年8月1日から7月31日までを判定の適用期間としており、自動的に更新されます。
(7月中旬ごろに新しい負担割合証を発行し郵送します。)
介護サービスを利用するときは、必ず被保険者証と一緒にサービス事業者や施設に提出してください。
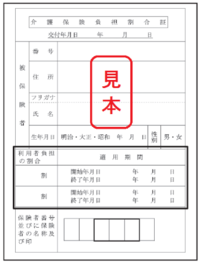 介護保険負担割合証(見本)
介護保険負担割合証(見本)施設入所者等の利用者負担軽減(介護保険負担限度額認定)
施設サービスを利用した時は、施設サービス費の1割(所得に応じて2割または3割)に加え、居住費(ショートステイの場合は滞在費)、食費および日常生活費(理美容代など)を支払います。
このうち、居住費および食費については、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用をもとに水準額が定められています。
※近年の高齢者世帯の光熱・水道料などや在宅する方との公平性等を総合的に勘案し、令和6年8月から居住費の負担額が60円(日額)引き
あがります。(利用者負担第1段階の多床室利用者については負担限度額に変更はありません。)
| 居住費(滞在費) | 食費 | |||
|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
| 2,066円 | 1,728円 | 1,728円(1,231円) | 437円(915円) | 1,445円 |
※特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用した場合の基準費用額は、( )内の金額が適用されます。
負担限度額認定
居住費および食費の負担額について、低所得の方(市町村民税が非課税世帯の方または生活保護を受けている方など)を対象に、その費用を軽減する制度があります。軽減の対象となるサービスは次のとおりです。
- 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
対象者と軽減後の負担限度額
本人及び世帯全員が市町村民税非課税であって、次の表の要件に該当する方
※夫婦のうち、1人だけ施設に入所されている場合など、別世帯になっている配偶者の課税状況、預貯金の状況も判定の対象になります。
※近年の高齢者世帯の光熱・水道料などや在宅する方との公平性等を総合的に勘案し、令和6年8月から居住費の負担額が60円(日額)が
引きあがります。(利用者負担第1段階の多床室利用者については負担限度額に変更はありません。)
介護保険施設等における居住費の負担限度額について
| 利用者負担の段階要件 | 居住費(滞在費) | 食費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設入所 | ショートステイ | ||
| 第1段階 | 老齢福祉年金の受給者である、又は生活保護の受給者であって、預貯金額が1,000万円(夫婦の場合は2,000万円)以下である。 | 880円 | 550円 | 550円(380円) | 0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 本人の年金以外の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80.9万円以下であって、預貯金額が650万円(夫婦の場合は1,650万円)以下である | 880円 | 550円 | 550円(480円) | 430円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階(1) | 本人の年金以外の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80.9万円超120万円以下であって、預貯金額が550万円(夫婦の場合は1,550万円)以下である | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 650円 | 1,000円 |
| 第3段階(2) | 本人の年金以外の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超であって、預貯金額が500万円(夫婦の場合は1,500万円)以下である | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
※第2号被保険者は、いずれの利用者負担の段階であっても、預貯金等の資産が1,000万円(夫婦の場合は2,000万円)以下であれば支給対象となります。
申請が必要です
認定を受けるためには申請が必要です。次の書類を窓口に提出してください。
- 介護保険負担限度額認定申請書 PDF (147.3KB)・WORD (24.1KB)
- 預貯金通帳の写し等
審査の結果、認定された方には介護保険負担限度額認定証を発行します。
限度額認定証は毎年8月1日から7月31日までを判定の適用期間としていますが、必要な方は毎年申請が必要です。
介護サービスを利用するときは、必ず被保険者証と一緒に施設等に提出してください。
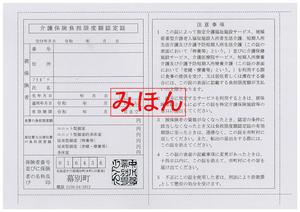 介護保険負担限度額認定証(見本)
介護保険負担限度額認定証(見本)
その他の利用者負担軽減
上記以外にも、低所得者に対して、次のような利用者負担軽減制度があります。
いずれも利用する際には申請が必要です。
| 制度名 | (1)社会福祉法人等利用者負担軽減 | (2)介護保険サービス利用者負担軽減 | (3)訪問介護利用者負担軽減 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用した場合に自己負担額を軽減します | (1)に該当しない介護保険サービスを利用した場合に自己負担額を軽減します | 訪問介護サービスを利用した場合に自己負担額を軽減します |
| 対象となる サービス |
|
|
|
| 軽減割合 | 利用者負担額、食費、居住費(滞在費)の25/100 | 利用者負担額、食費、居住費(滞在費)の25/100 | 利用者負担額の40/100 |
| 該当要件 |
|
| |
| 申請書類 | 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 (PDF・Word) | 介護保険サービス利用者負担軽減対象確認申請書 (PDF・Word) | 訪問介護利用者負担額軽減認定申請書 (PDF・Word) |
| 認定証見本 | 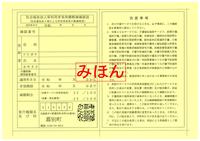 |  | 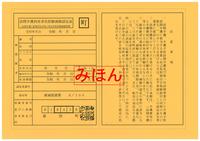 |
各制度の有効期間
それぞれの認定証は、毎年8月1日から7月31日までを判定の適用期間としていますが、必要な方は毎年申請が必要です。
(7月中旬ごろに新しい認定証を発行し郵送します。)
介護サービスを利用するときは、必ず被保険者証と一緒に施設等に提出してください。
境界層該当者の軽減制度
介護保険サービスの利用者負担の軽減をすれば生活保護受給に至らない場合に、より低い利用者負担や介護保険料の基準を適用する制度です。
現在適用されている利用者負担や介護保険料を負担すると生活保護が必要となる介護保険サービス利用者が、それより低い基準の利用者負担や介護保険料を適用すれば生活保護を必要としなくなる場合に、十勝総合振興局で「境界層該当証明書」が発行されます。
境界層に該当するかどうかは、生活保護の申請が必要ですので、十勝総合振興局社会福祉課へご相談ください。
措置の内容
- 介護保険料の滞納があっても給付制限(給付額の減額)を行いません。
- 介護保健施設における居住費、滞在費の負担限度額をより低い段階とします。
- 介護保健施設における食費の負担限度額をより低い段階とします。
- 高額介護サービス費を算出する際の負担上限額の段階を下げます。
- 介護保険料の所得段階をより低い段階とします。
利用者負担額の減額・免除
被保険者の方が、災害などにより著しい損害を受けたり、事業の休廃止等で収入が著しく減少したなどの事情で、サービス利用料の支払いが困難となった場合などには、利用者負担額を減額したり、免除したりする制度があります。
詳しくは保健課介護保険係までお問い合わせください。