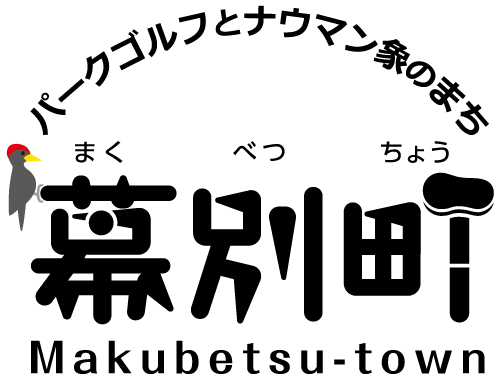介護(予防)サービスを利用するためには
介護(予防)サービスの内容は、その人の心身の状態や生活環境に応じて、どのようなサービスを「いつ」「どのくらい」利用するか異なります。
そのため、一人ひとりに合った計画を作成する必要があります。
この計画をケアプランと言います。
ケアプランの作成は、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに依頼します。
要支援1または要支援2の方の場合
地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼してください。
地域包括支援センターの担当者または地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーとの話し合いの中で、どのようなサービスを利用するか検討します。
※介護予防小規模多機能型居宅介護を利用する場合は、直接利用する事業所に依頼してください。
要介護1から要介護5までの方で、在宅サービスを利用する場合
居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼してください。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーとの話し合いの中で、どのようなサービスを利用するか検討します。
※次のサービスを利用する場合は、直接利用する事業所に依頼してください。
- 特定施設入居者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
要介護1から要介護5までの方で、施設サービスを利用する場合
入所を希望する施設に直接申し込みをします。
その施設の担当ケアマネージャーが利用者にあったケアプランを作成します。
ケアプランの作成
- ケアマネジャーからケアプランの原案が提示され、利用者やその家族、サービス事業所が、その原案について検討を行います。
- サービスの種類や利用回数などを盛り込んだケアプランが完成し、利用者が同意したら、サービスの提供事業者と契約を結びます。
- ケアプランに基づいて、介護(予防)サービスの利用を開始します。
介護(予防)サービスの利用
介護保険で利用できるサービスには、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなどがあります。
要介護(要支援)の認定結果に応じて、自分に必要なサービスを組み合わせて利用することができます。
※認定結果によっては利用できないサービスがあります。
自己負担額の目安など、詳しい内容はそれぞれのサービスの種類をクリックしてください。(独立行政法人福祉医療機構の運営するWAMNETのサービス一覧・紹介ページ(外部リンク)にリンクしています。)
| 分類 | サービスの種類 | サービスの内容 |
|---|---|---|
| 居宅サービス | 訪問介護(外部リンク) (ホームヘルプサービス) | ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴などのお世話をしたり、調理、掃除などの援助をします。 ※要支援の方は総合事業の訪問型サービスになります。 |
| 訪問入浴介護(外部リンク) | 移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。 | |
| 介護予防訪問入浴介護(外部リンク) | ||
| 訪問看護(外部リンク) | 看護師が自宅を訪問し、病状の観察、点滴や尿管カテーテルなどの管理を行います。 | |
| 介護予防訪問看護(外部リンク) | ||
| 訪問リハビリテーション(外部リンク) | 理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。 | |
| 介護予防訪問リハビリテーション(外部リンク) | ||
| 居宅療養管理指導(外部リンク) | 医師、歯科医師、薬剤師や管理栄養士などが自宅を訪問して、薬の飲み方など医学的な管理や指導を行います。 | |
| 介護予防居宅療養管理指導(外部リンク) | ||
| 通所介護(外部リンク) (デイサービス) | デイサービスセンターなどで、食事や入浴、レクリエーションなどを行います。 ※要支援の方は総合事業の通所型サービスになります。 | |
| 通所リハビリテーション(外部リンク) | 介護老人保健施設や医療機関で、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを行います。 | |
| 介護予防通所リハビリテーション(外部リンク) | ||
| 短期入所生活介護(外部リンク) (ショートステイ) | 短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練などを行います。 | |
| 介護予防短期入所生活介護(外部リンク) | ||
| 短期入所療養介護(外部リンク) (医療型ショートステイ) | 短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練、医療措置、リハビリテーションなどを行います。 | |
| 介護予防短期入所療養介護(外部リンク) | ||
| 特定施設入居者生活介護(外部リンク) | 有料老人ホームやケアハウスなどに入所している人に、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練などを行います。 短期間の利用もできます。 | |
| 介護予防特定施設入居者生活介護(外部リンク) | ||
| 福祉用具貸与(外部リンク) | 日常生活の自立を助けるための用具を貸し出します。 対象となる福祉用具の種類はそれぞれの紹介ページをご参照ください。 | |
| 介護予防福祉用具貸与(外部リンク) | ||
| 福祉用具購入(外部リンク) | 次の福祉用具を対象として、購入費用の一部(7割~9割)を支給します。
| |
| 介護予防福祉用具購入(外部リンク) | ||
| 住宅改修(外部リンク) | 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、改修費用の一部(7割~9割)を支給します。 工事をする前に、ケアマネジャーの確認を受けたうえで、事前申請が必要です。 | |
| 介護予防住宅改修(外部リンク) | ||
| 地域密着型サービス ※原則として事業所と同一市町村の被保険者しか利用できません。 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(外部リンク) | 日中、夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行います。 ※要支援の方は利用できません。 |
| 夜間対応型訪問介護(外部リンク) | 夜間において、定期的な巡回による訪問介護サービス、利用者の求めに応じた随時の訪問介護サービス、利用者の通報に応じて調整、対応するオペレーションサービスを行います。 ※要支援の方は利用できません。 | |
| 地域密着型通所介護(外部リンク) (小規模デイサービス) | 小規模の老人デイサービスセンターなどにおいて、日帰りで介護や生活機能訓練を行います。 ※要支援の方は総合事業の通所型サービスになります。 | |
| 認知症対応型通所介護(外部リンク) | 認知症の状態にある方に、デイサービスセンターなどで、食事、入浴、排せつなどの介護や機能訓練を行います。 | |
| 介護予防認知症対応型通所介護(外部リンク) | ||
| 小規模多機能型居宅介護(外部リンク) | 小規模歌機能型事業所で、食事、入浴、排せつなどの介護機能訓練などを行い、また、心身状況や利用者の希望に応じて介護職員が自宅を訪問したり、短期間の宿泊を受けられるサービスを行います。 | |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護(外部リンク) | ||
| 認知症対応型共同生活介護(外部リンク) (グループホーム) | 認知症の方に、家庭的な雰囲気の中で、共同生活をしてもらいながら、食事、入浴、排せつなどの介護や機能訓練を行います。 ※要支援1の方は利用できません。 | |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護(外部リンク) | ||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護(外部リンク) | 小規模な有料老人ホームなどやケアハウスなどに入所している人に、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練などを行います。 短期間の利用もできます。 | |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(外部リンク) | 小規模な特別養護老人ホームに入所している人に、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練などを行います。 ※原則として要介護3から要介護5までの方に限りサービスを利用できます。 | |
| 施設サービス ※要支援の方は施設サービスは利用できません。 | 介護老人福祉施設(外部リンク) (特別養護老人ホーム) | 寝たきりや認知症などで常に介護が必要な方のための施設です。施設で食事や入浴、排せつなどの日常生活の介護や機能訓練を行います。 ※原則として要介護3から要介護5までの方に限りサービスを利用できます。 |
| 介護老人保健施設(外部リンク) | 病状が安定し、在宅復帰に向けてリハビリテーションを中心とした介護が必要な方が入所します。短期集中型の介護や看護、リハビリテーションなどを行います。 | |
| 介護療養型医療施設(外部リンク) | 病状が安定し、長期の療養が必要な方が入院する施設です。看護、医学的な管理のもとでの介護や機能訓練、必要な医療を行います。 | |
| 介護医療院(外部リンク) | 主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)を一体的に行います。 |
介護サービスの利用限度額
在宅で介護保険のサービスを利用する場合、要介護状態区分ごとに1か月の給付を受けられる区分支給基準限度額が次のとおり定められています。
(サービスによって区分支給限度基準額の対象となるもの、ならないものがあります。)
| 要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |