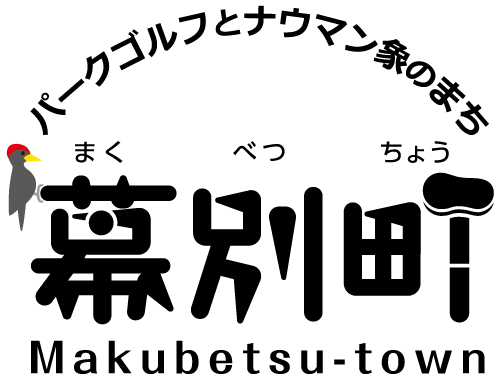介護保険料のしくみ
介護保険の費用は、利用者が介護サービスを利用するときの負担(所得等に応じて1割~3割)を除いた額を、40歳以上の人が納める保険料と公費(国、道および町の負担金)でそれぞれ50%ずつ負担しており、このうち、65歳以上の人が負担する保険料は全体の23%となっています。
個人の保険料は、第1号被保険者本人の所得と、市町村民税の課税状況および世帯の市町村民税課税状況によって決まります。
令和6年度~令和8年度介護保険料(第9期介護保険事業計画)
| 所得段階 | 本人の属する世帯の状況 【対象者】 | 本人の状況 【対象者】 | 年額保険料(保険料割合) | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 世帯員全員が非課税の方 | 老齢福祉年金受給者の方、生活保護受給者の方 課税年金収入額と年金所得以外の合計所得金額の合計額が80.9万円以下の方 | 19,400円(基準額×0.285) | |
| 第2段階 | 第1段階に該当しない方で 課税年金収入額と年金所得以外の合計所得金額の合計額が120万円以下の方 | 27,200円(基準額×0.4) | ||
| 第3段階 | 上記に該当しない方 | 46,700円(基準額×0.685) | ||
| 第4段階 | 世帯員に課税者がいる方 | 本人が非課税の方 | 課税年金収入と年金所得以外の合計所得金額の合計額が80.9万円以下の方 | 57,900円(基準額×0.85) |
| 第5段階 | 上記に該当しない方 | 68,200円(基準額×1.0) | ||
| 第6段階 | 本人が課税の方 | 合計所得金額が120万円未満の方 | 81,800円(基準額×1.2) | |
| 第7段階 | 合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 88,600円(基準額×1.3) | ||
| 第8段階 | 合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 102,300円(基準額×1.5) | ||
| 第9段階 | 合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 115,900円(基準額×1.7) | ||
| 第10段階 | 合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 129,500円(基準額×1.9) | ||
| 第11段階 | 合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 143,200円(基準額×2.1) | ||
| 第12段階 | 合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 156,800円(基準額×2.3) | ||
| 第13段階 | 合計所得金額が720万円以上の方 | 163,600円(基準額×2.4) | ||
※「課税年金収入額」とは、老齢年金や退職年金などの市町村民税の課税対象となる年金収入額で、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などの年金収入額は含みません。
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、令和3年度から給与所得や公的年金に係る雑所得がある場合は、税制改正の影響を受けないように調整します。
※介護保険料は所得状況に応じて負担する仕組みとなっており、介護保険料の算定に用いる所得指標は次のようになっています。
- 第1~5段階の介護保険料の算定に用いる所得指標
…「課税年金収入額」+(「合計所得金額」-「長期・短期譲渡所得に係る特別控除額」-「年金収入に係る所得」) - 第6~13段階の介護保険料の算定に用いる所得指標
…「合計所得金額」-「長期・短期譲渡所得に係る特別控除額」
年度途中で第1号被保険者の資格を取得された方の保険料の計算
介護保険料は資格を取得した月からかかります。65歳に達した人は、誕生日の前日、65歳以上の人で幕別町に転入してきた人は転入日に、それぞれ資格を取得し、その月から保険料が月割計算されます。
| 資格取得理由 | 資格取得日 | 保険料の計算 |
|---|---|---|
| 65歳に到達 | 65歳の誕生日の前日 | 誕生日の前の日の属する月から計算されます。 |
| 幕別町に転入 | 転入日 | 転入日の属する月から幕別町で計算されます。 |
年度途中で第1号被保険者の資格を喪失された方の保険料の計算
| 資格喪失理由 | 資格喪失日 | 保険料の計算 |
|---|---|---|
| 死亡 | 死亡日の翌日 | 死亡日の属する月の前の月まで計算されます。 ※死亡日が月の末日の場合は死亡日の属する月までです。 |
| 他市区町村へ転出 | 転出確定日 | 転出確定日の属する月の前の月まで幕別町で計算されます。 |
保険料の納め方
保険料の納め方には、「普通徴収(窓口納付や口座振替などによる個別納付)」と、「特別徴収(年金からあらかじめ差し引くことによる納付)」の2種類があります。
通常は普通徴収から保険料の納付を開始し、年金受給額が年額18万円以上の人は、おおむね半年程度で特別徴収に切り替わります。
※普通徴収と特別徴収の切り替わりは自動的に行われます。被保険者自身が選択することはできません。
※特別徴収となっている人で、年度の途中に所得更正などで保険料が増額となった場合は、増額となった差額分は普通徴収になり、一時的に特別徴収と普通徴収が同時に生じることがあります。
普通徴収による納付
普通徴収となるのは次のような場合です。
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の人(対象となる年金には優先順位があり、優先順位が低い年金で18万円以上の年額となる場合でも普通徴収となることがあります。)
- 年度の途中で65歳に達した人や、転入してきた人で、特別徴収に切り替わるまでの間
- 年度途中で保険料段階が変更となった人
- 年金支払者の事情により特別徴収ができなくなった人
納付方法
次の場所に納付書を持参し、納めてください。
役場会計課、忠類総合支所、札内支所、糠内出張所、駒畠出張所、金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局窓口、コンビニエンスストア
(納付書の裏面をご確認ください。)
※令和2年4月1日より、納付書に印字されているバーコードを読み取ることで、スマートフォンアプリからも納付することが可能です。
※期限が来ても納め忘れがなく、納めに行く手間も省くことができる、便利な口座振替をご利用ください。
納付期間(令和6年度)
| 期別 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 令和6年7月1日 |
| 第2期 | 令和6年7月31日 |
| 第3期 | 令和6年9月2日 |
| 第4期 | 令和6年9月30日 |
| 第5期 | 令和6年10月31日 |
| 第6期 | 令和6年12月2日 |
| 第7期 | 令和6年12月25日 |
| 第8期 | 令和7年1月31日 |
| 随時期(第9期) | 令和7年2月28日 |
| 随時期(第10期) | 令和7年3月31日 |
| 随時期(第11期) | 令和7年4月30日 |
※納期限(口座振替日)は各月の月末(12月は25日)ですが、その日が土曜日、日曜日または祝祭日の場合は翌平日になります。
特別徴収による納付
特別徴収の対象となる年金を、年額18万円以上受給している人が対象となり、年金の定額支払いの際に、あらかじめ保険料が差し引かれます。
特別徴収には、仮徴収と本徴収があります。
仮徴収(4月・6月(・8月))
前年度から引き続き特別徴収となる人は、その年度の保険料の額が正式に決定する(毎年6月)までの間、暫定的に前年度2月分と同じ額を各月に徴収します。ただし、8月については、所得の状況やその他の事情を勘案して、金額を調整することがあります。
本徴収(10月・12月・2月)
6月に決定する年間の保険料額から、仮徴収期間に徴収した保険料額を差し引いた残りの額を、3回に分けて納めます。
保険料の納付が困難なとき
被保険者の方が、災害などにより著しい損害を受けたり、突発的な事業の休廃止などで著しく収入が減少したなどの事情で保険料を納めることが困難なときは保険料の納付を一定期間猶予したり、減免することができる場合があります。
詳しくは、各納期限の7日前まで、または特別徴収月の前々月の15日までに、保健課介護保険係までご相談ください。