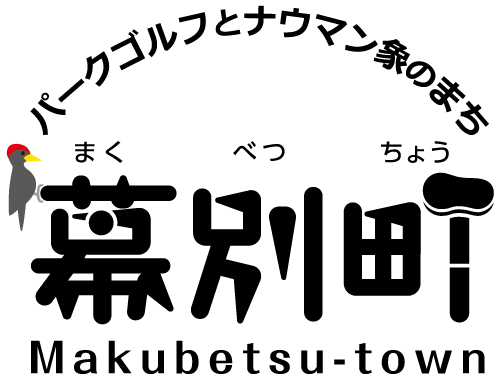用語解説
議会で使われる「ことば」は、地方自治法などに出てくる専門用語が数多くあります。少しでもみなさんに分かってもらえればと思い「用語解説」を用意しました。
目次に書かれているアンダーラインの引かれたことばをクリックすると、その解説のところにジャンプします。
※この用語解説は、幕別町の条例等に定められている規定に基づいて作成しており、他市町村と同じ取り扱いとは限りません。
目次
か行:開会 会期 開議 議員定数 議会 議会の委員会 継続審査 決議
さ行:採決 散会 執行機関 趣旨採択 所管事務調査 除斥 審議未了 請願 政務活動費 専決処分
な行:認定
ま行:みなし採択
や行:予算提案権
あ行
同一会期中に一度議決された事件については、再び議決しないこと。
提出された請願のうち、一部の項目又は部分を採択すること。
委員会における請願の審査結果は、採択にすべきものと不採択にすべきものとの二者択一であるが、実際には、請願の内容の全部又は一部に賛成しうる場合と、賛成できない場合とがある。請願は、請願そのものを議決するものではなく、それに対する議会の意思を決定するもので、その内容を修正して採択することはできないので、このような便法によってできるだけ請願の趣旨を活かすことが望ましい。
議事日程の一部を議了しないか又は全部を終わらず、その日の日程を他の日に延ばして、会議を閉じること。
か行
議会を開き、法的に活動しうる状態に置くこと。
議会が議会としての権限を行使し、法的に活動することのできる期間のこと。
その日の会議を開くこと。
議員の定数は、地方自治法により条例で定めることとされており、本町の場合は19人である。
地方公共団体に置かれる合議制の議事機関で、住民を代表する公選の議員をもって構成されている。
議会の内部機関として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置されている。
条例で、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会を置くことができる。
会議に付された事件について、会期中に議了できず、付託を受けた委員会が閉会中に引き続き審査を行うこと。
会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しないとする、会期不継続の原則の例外である。
議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由でなされる議決のこと。
さ行
会議で表決に付す問題に対して、議長が出席議員に賛否の意思表示を求め、その各別の意思表示を集計すること。
その日の議事日程に記載されている事件のすべてを終了して、その日の会議を閉じること。
行政の執行権限をもち、所掌事務について、地方公共団体の意思を自ら決定し、外部に表示しうる議会のこと。
地方公共団体には、長(町長)以外に、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会等の執行機関がある。
請願の願意は妥当であるが、実現性の面で確信がもてないといった場合に、不採択とすることもできないとしてとられる請願に対する決定方法。
常任委員会は、その部門に属する事務を調査し、議会運営委員会は、議会の運営に関する事項等について調査を行う権限がある。委員会固有の権限に基づく所管事務の調査のこと。
議会における審議の公正を期するために、審議事件と一定の利害関係のある議員は、その審議に参与することができない。
議員のほか、父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹が対象とされている。
議会の会議に付議された事件が、会期中に議了せず、継続調査の決定もなされないままに、会期を終えることになった場合のこと。
審議未了となった場合は、廃案となる。
住民が、国又は地方公共団体等の公共団体に対し、一定の措置をとるよう、あるいはとらないように希望し、申し出ること。
法律的に保証された請願権に基づくものであるが、単に希望を述べるにとどまることから、議会で採択されて、執行機関や内閣に意見書が送付されても、願意に沿った措置がとられるかどうかは、執行機関や内閣の判断による。
請願には、紹介議員が必要となる。
地方公共団体が、議会議員の調査研究等に必要な経費の一部として、議会の会派又は議員に対して交付することができる金銭的給付。
本町では支給していない。
議会が議決又は決定すべき事件について、長が議会に代わって処分すること。
「法律の規定による専決処分」と「議会の委任による専決処分」とがある。
除雪費などは、議会に付議する時間がないとして専決処分されることがある。
た行
議会の権威を保持し、会議の運営を円滑に進行させるために、議長に与えられた議場の秩序維持に関する権限。
国又は地方公共団体等の公の機関に対し、一定の事項に関して利害関係のある者が、その実情を訴え、相当の措置を要望する行為。
法律上保証された権利ではなく、事実上の行為にすぎない。
陳情には、紹介議員は必要がない。
付議事件の有無にかかわらず、定例的に招集される議会の会議。
招集回数は、条例で定めることができる。(平成15年までは年4回以内とされていた。)
議会の会議において、表決の前に、議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明すること。
な行
公の機関がある事実又は法律関係の存否を確認すること。
地方自治法上、議会に地方公共団体の決算の認定権を認めているが、決算が認定されなくても、決算の法的効力には影響はない。ただ、長の政治的責任は残る。
は行
議会の会議におてい、議員が議事の対象となるべき議案等を議長に提出すること。
一般選挙後に初めて招集された議会の会議のこと。
したがって、通常は4年に1回となる。
議会の意思決定に個々の議員が参加するための手段で、議題に対して賛成、反対の意思表示をすること。
議案などの議会の審議に付される事件。
議会の議決を要する事件について、議会の議決に先立って詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に審査を委託すること。
全議員で構成する議会の会議のこと。
議会としての権限、能力は、本会議に認められており、法律上要求される議会の議決、同意、決定、承認、採択等は、本会議で行わなければ、法的な効力は生じない。
ま行
同一会期中において、すでに同一趣旨、同一目的の議案又は請願が議決されている場合の請願について、一事不再議の原則に触れるので、議決することなく、すでになされて議案、請願の結果により採択又は不採択とみなして処理する取り扱い。
や行
予算を議会に提出する権限のこと。
予算は、議会の議決によって定められるが、予算を調整し、議会へ提案する権限は長にあり、議員や長以外の執行機関である委員会及び委員も提案権はない。
ら行
議会の招集日に招集に応じた議員が定数の半数に達せず、会議を開けなかった場合のこと。
定例会のほかに、臨時の必要があるため、特定の事件に限って審議するために随時招集される議会。