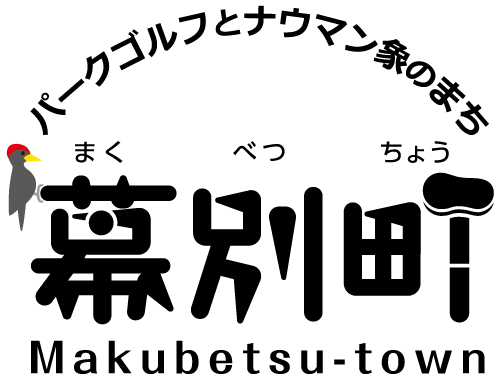令和6年度の「町長への手紙」
- 投票所の削減反対について
- 新川近隣センターについて、道路等について
- 町民プールの使用料について
- 忠類コミセンの大ホールにエアコンを付けてほしい
- 町道忠類北4線と国道236号線との交差点に注意喚起看板を設置してほしい
- 道の駅の建設とコミバスの運行について
- オンラインワンストップ申請の導入について
- 令和6年能登半島地震の義援金(募金)について
- アイヌ文化拠点空間整備の施設建設位置等について
- 途別小学校の閉校について
- ゼロカーボンシティの実現に係る電気自動車の考え方について
- 幕別町内の学校におけるいじめ問題について
- 学童保育料について・自転車用ヘルメットの助成について
投票所の削減反対について(男性 幕別市街地)
内容
新しい投票所の所在の説明もなく、一方的に投票所を削減している。
回答
投票所の削減について、ご意見をいただきありがとうございました。
地方公共団体が担う選挙事務は、地方自治法の規定に基づき、選挙が公正に行われるよう町長から独立した機関として設置された選挙管理委員会において管理執行されております。(議会で選挙された民間人4名の委員によって構成されています。)
このたびの投票所の再編は、幕別町選挙管理委員会において、公職選挙法の規定に基づき適正な手続きを経て決定されたものであります。
以下、幕別町選挙管理委員会からの回答に基づき、お答えいたします。
幕別町選挙管理委員会では、平成18年2月の町村合併以来、旧幕別町で定めていた22か所に旧忠類村で定めていた1か所を加えた23か所の投票所を設置し、選挙事務の効率的な運営に資するよう、開票事務の効率化や選挙ポスター掲示場の見直し等を行いながら、公正で円滑な選挙事務を執行してきました。
近年の投票状況は、平成15年に創設された期日前投票制度の浸透により、投票総数における期日前投票の割合が回を重ねるごとに増加し、相対的に当日の投票者数が減少してきております。(令和6年衆議院選挙における投票者数13,571人、うち期日前投票者数5,760人(42.44%))
一方、投票所運営にあたっては、投票立会人などの投票所における従事要員について、担い手の確保が困難な状況が続いていることや、事務従事する職員の負担、加えて、投票所は幅広い年齢層の方が訪れる場所であることから、土足化やバリアフリー化といった投票環境について、改めて見直しをする必要があること等の課題がありました。
これらの状況から、幕別町選挙管理委員会において、すべての有権者にとってより投票しやすい環境を整えるとともに、この先20年で約15%の減少が見込まれているという本町の人口推計から、20年後を見据え、現在の23の投票区から11の投票区へと再編が行われたところであります。
この度の再編にあわせ、すべての投票所において靴を脱がずに投票をすることができる「土足化対応」とするほか、投票所への移動が困難な方に対する移動支援の拡大が行われることとなっております。
幕別町選挙管理委員会が再編の検討を進めるにあたっては、町議会に対しての説明をはじめ、投票所が変更となる行政区の町内会長を対象とした意見交換会を開催しご意見を伺ったほか、広報まくべつ(令和6年10月号から12月号まで)において投票区見直し案の周知を行い、住民の皆さんに検討状況をお知らせしてまいりました。
その後、令和7年1月に実施したパブリックコメント(住民からの意見募集)を経て、3月3日開催の幕別町選挙管理委員会の会議において正式に投票区の再編が決定されたところであります。
今後においては、町広報紙や町HPへの掲載をはじめ、各公共施設への掲示をするなど、新たな投票区・投票所についての周知を図るとともに、実際に選挙が行われる際には、投票所入場券の送付にあわせて新たな投票所のご案内が送られる予定となっております。
混乱のない形で選挙事務が執行されるよう周知徹底に努めてまいります。
担当部署
選挙管理委員会事務局
新川近隣センターについて、道路等について(60代男性 幕別市街地)
内容
(1)新川近隣センターの建て替えを行わないのか。
(2)新川近隣センターの入口を農作業機の出入りが可能となるよう拡幅してほしい。
(3)冬期間の散歩コースとしたいため、新川32号線と新川14線を除雪してほしい。
(4)新川から大豊につながる道路の造成を検討いただけないか。
回答
(1)、(2)について回答したします。
ご意見・ご提案の1点目にある近隣センターの建替えにつきましては、幕別町公共施設等総合管理計画において、集会施設は構造補強等により長寿命化を図りながら将来の人口動向や地域の実情、施設の利用実態などを踏まえ、地域住民との合意形成の下、集約化・複合化による施設規模の適正化に努めることとしており、建築から30年を経過している施設の中から、老朽化が著しい施設について順次建替えや改修を行っております。
新川近隣センターは、昭和51年に建築され、平成21年に改修を行っておりますことから、町内に設置されている46か所の近隣センターの中でも比較的健全な状態を保っており、当面の間改修の予定はありませんのでご理解をお願いします。
また、近隣センターを含む町内の公共施設につきましては、「公の施設の使用に関する規則」でそれぞれ使用時間を定めており、災害時等の避難所としての利用など、特別な事情がない限り規則で定められた時間内の使用としております。
なお、ご提案いただいた世代間交流等の場としての利用につきましては、近隣センターの設置目的である地域コミュニティの活性化に寄与するものと考えられますので、地域や人との繋がりを支えるコミュニティスペースとして、引き続き施設を効果的に活用していただきたいと考えております。
ご意見・ご要望の2点目にある近隣センター入口の拡幅につきましては、近隣センターは地域における集会施設として位置付けており、主に普通自動車での来館を想定しておりますことから、現時点で町として対応する考えはありません。
交通量の多い国道からの出入りとなることから、農作業機での来館は大変危険ですので、普通自動車をご利用いただき、十分に安全確認を行った上で来館していただきますようお願いします。
(3)町道除雪について、ご意見をいただきありがとうございます。
町道除雪は、緊急医療や公共交通の通行機能を確保するとともに、町民生活など一般の交通に支障を及ぼさないよう道路を常に良好な状態に保つため、町道1,028路線、約882kmのうち、937路線、約650kmの車道除雪を実施しております。
町では、限られた除雪車、限られた時間、限られた予算で、町道全路線を除雪することは物理的に困難なため、優先的に除雪する路線を決め、住宅が張り付いていない町道や専ら夏期間の営農に使用する農道など冬期間に利用のない町道については、除雪を行っていないのが現状となっています。
ご要望がありました「新川32号線」と「新川14線」につきましても、住宅が張り付いておらず、冬期間に営農等の利用がないことから、除雪を行っておりませんが、町全体の効率的で効果的な除雪体制を維持するためにも、ご理解とご協力をお願いいたします。
(4)町道の検討について、ご意見をいただきありがとうございます。
道路整備は、多額の費用を要するため、国や道の補助金を活用しながら、町総合計画に位置付け、計画的に整備を実施していますが、交通量が少ない農村部などの道路につきましては、国土交通省所管の道路事業での採択が難しいことから、道営水利施設等保全高度化事業(畑地帯総合整備事業)を活用するなど、財源の確保と整備に時間を要している状況となっております。
このため、ご要望の路線につきましては、他地区と同様に道営事業の新たな事業地区を立ち上げる際に、事業効果を検証し、農道としての採択要件を満たした場合に、北海道へ要望したいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
担当部署
(1)(2)住民生活部住民課
(3)建設部土木課
(4)経済部農林課
町民プールの使用料について(70代女性 札内市街地)
内容
町民プールの使用料が高いと感じます。
回数券やシーズン券をつくっていただけないでしょうか。
回答
町民プールの使用料について、ご意見をいただきありがとうございました。
町が提供する公共サービスは、広く町民の皆様から徴収した税金により賄われておりますが、全てを税金で賄うと、サービスを受ける方と受けない方との不公平が生じることから、受益者負担の原則に基づき、サービスを受ける方に一定の費用等の負担をお願いすることとして、令和4年10月1日から基本方針に基づいた料金を適用してまいりました。
この使用料の見直しに伴う負担の急激な増減を抑制するため、令和4年10月1日から令和7年3月31日までは激変緩和措置として、町民または町内団体の使用につきましては、使用料の5割を減額してきたところであり、4月1日からはこの措置がなくなるため、算定した使用料をご負担いただくこととなります。
なお、今回ご意見をいただきました町民プールの使用料の算定方法は、町民プールの施設全体に係る人件費や物件費の合計を年間の利用人数で除した金額を1人当たりの原価として、受益者の負担割合の50%を乗じて算出した金額の100円未満を切り捨てたものを個人利用にかかる使用料としております。
いただいたご意見に、健康のために町民プールを利用しているのでできる限り低廉に、という記載がありましたが、町内の健康維持・増進のために使っていただいているその他の施設も同様に、受益者負担の原則に基づき使用料をご負担いただくこととしております。
また、回数券やシーズン券をつくってほしいというご意見も併せていただきましたが、町民プールの運営にかかる費用を利用人数から考慮した受益者負担割合で使用料を設定しており、今のところこれらの割引券については考えておりませんが、今後の社会情勢の変化などを見極め、対応を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
担当部署
企画総務部政策推進課
忠類コミセンの大ホールにエアコンを付けてほしい(70代女性 忠類市街地)
回答
忠類コミュニティセンターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
近年の気候変動の影響から、全国的にも夏場の気温が記録的な猛暑となり、十勝においても、気温が30度を超える日が連続するなど、厳しい暑さが増加している傾向にあります。
こうした状況を背景に、町では、公共施設のうち気温の上昇する時間帯に長時間にわたり利用者が滞在する、小・中学校の各教室(屋体を除く)や保育所、学童保育所などの施設にエアコンを設置し、健康面に配慮した環境を整えてきたところであります。
一方、コミュニティセンターや近隣センターなど利用者自らが利用時間帯を選択できる公共施設については、常時高温下で過ごさざるを得ない保育所や小中学校と比較して、エアコンの依存度に差異があることや冷房設備の導入には多額の費用を要することなどから、現在のところ忠類コミュニティセンターの各室にエアコンなどの冷房設備を設置する考えには至っておりません。
熱中症は、特に体温調整機能が弱い子どもや調整機能が低下している高齢者が発症する場合が多い傾向にあるといわれており、その予防には「暑さを避ける」ことが最も重要とされております。
このため、気温の上昇する時間帯での活動や危険な暑さが予測される場合には、サークル活動を控えるなどの熱中症予防対策をとる必要がありますが、忠類コミュニティセンターは、避難所として位置付けている施設でもありますので、地球温暖化による猛暑に備えた冷房設備の個数や能力などを検証し、引き続き、公共施設における利用環境の改善に向けた検討を進めてまいります。
担当部署
忠類総合支所地域振興課
町道忠類北4線と国道236号線との交差点に注意喚起看板を設置してほしい(30代男性 町外)
回答
『町道忠類北4線と国道236号線との交差点への注意喚起看板の設置』について、ご意見をいただきましてありがとうございます。
ご意見のありました町道忠類北4線と国道236号線との交差点は、帯広広尾自動車道忠類大樹インターチェンジが現在の終点でありますことから、このインターチェンジを降りて町道忠類北4線を経由し、国道236号線との交差点で大樹町方面へ右折する車両が多い状況にあります。
国道236号線を北進してきた車両が忠類大樹インターチェンジに向かうため、町道忠類北4線へ左折する箇所には左折専用車線が設けられておりますが、特に大型車両が左折専用車線を走行する際に、後続の国道を直進する本線上車両が、町道側の車両からは大型車に隠れて見えづらくなり出会い頭の事故が発生しております。
この交差点での事故については帯広警察署や忠類駐在所とも情報共有を行っており、令和3年1月以降の4年間で12件の事故を把握しておりますことから、これまでも国道を管理する北海道開発局や警察と事故防止策について協議をしてまいりました。
今年5月には警察を通じて北海道開発局に対し国道側に注意喚起の看板等の設置や、区画線の整備を依頼しております。
町では、今後同様の事故を抑止するため町道側の交差点付近に注意喚起の看板を設置いたします。
また、従来から町道の国道交差点付近には「交差点注意」の路面表示をしておりますが、表示が薄くなっておりますことから雪解け後早急に路面表示の修復も行ってまいります。
担当部署
忠類総合支所経済建設課
道の駅の建設とコミバスの運行について(60代女性 札内市街地)
内容
(1)道の駅の建設を要望します。
(2)コミバスの土日運行やイベント時の臨時運行について要望します。
回答
お寄せいただいたご意見に、次のとおり回答いたします。
(1)幕別町におきましては、合併前の旧・忠類村の地域において、平成5年に道内では9番目となる道の駅・忠類を設置し、焼き立てのパンや特産であるゆり根を使った商品の販売など、十勝ナウマン温泉ホテルアルコやナウマン公園、菜の館ベジタ、白銀台スキー場などの周辺施設と一体となって、観光振興に寄与してきたところです。
一方で幕別・札内地域におきましても、道の駅建設の機運の高まりから幕別町商工会が実施主体となり、平成22年にスマイルパーク北側駐車場において、実験店舗を開設し、町内の生産加工食品の販売やパークゴルフなど観光情報の発信を行い道の駅建設を模索したところですが、その後の意向確認では、将来的に道の駅への出店を希望する事業者がなく、協議を終えた経緯があります。
道の駅の建設に関しましては、多額の整備資金が必要なほか、場所の選定、持続可能な運営の確保など多くの課題があり、現時点では建設の予定はありませんが、地元の農畜産物や加工品などが気軽に購入できるよう、幕別町観光物産協会や幕別町商工会、各農協など関係機関に働きかけるとともに、町としましても学校給食などを中心に地産地消の取組を進めてまいります。
(2)町内を運行するコミュニティバスは、幕別地域・札内地域それぞれの公共交通空白地域から、最寄りの鉄道や路線バスに接続させる路線として、平成25年10月から十勝バス株式会社が運行主体となり運行を開始しております。
この運行では、幹線に接続する支線に対して国の補助金(地域内フィーダー系統補助金)を活用しており、公共交通空白地域から地域内の最寄りの駅やバス停までの接続を目的としています。
そのため、鉄道や路線バスと競合するような、地域を越える運行は認められないところであります。
また、運行時間の設定においては、最も利用頻度の高い朝から夕方の時間帯に発着時間の設定をしており、高齢者をはじめ、通学や通勤、通院や買い物など地域の皆さんの生活を支える交通手段、いわゆる「地域の足」としてご利用いただけるよう配慮しております。
休日の運行にあたっては、本格運行前の試験運行において、休日の利用者が少なかったことから、平日のみの運行としてスタートしております。
その後、平成31年2月、令和元年7月の全ての休日においても休日試験運行を行いましたが、いずれも平日の半数以下の利用実績となり多くの需要を見込むことはできませんでした。この利用者減少の要因は、土日における病院の休診、金融機関の休業や学校の休校などと捉え、休日の運行を見送っているところであります。
コミュニティバスは、予め時間と路線を設定して運行する公共交通のため、臨時運行する場合においては、住民と関係機関の代表者で組織する「幕別町地域公共交通活性化協議会」においてその必要性と公益性を判断し、北海道運輸局への必要な届出を経て臨時運行を実施しており、これまでに、選挙管理委員会からの要請を受け、期日前投票期間中の土日運行をしております。
ご要望のコンサートやイベント会場までの輸送に関しては貸切バスの運行やシャトルバスが一般的であり、主催者の考えにより手配されているものと認識しておりますが、町内のイベント会場においては、十分な駐車スペースに加え、輸送に係る費用対効果が見込めないことが、運行していない要因であると推察しております。
今後においても、地域の足としての地域公共交通の利用促進に向け、乗降調査やアンケート調査などを通じ住民ニーズの把握に努め、より使いやすく便利なコミュニティバスを目指してまいりたいと考えております。
この度は、貴重なご意見ありがとうございました。
担当部署
(1)経済部商工観光課
(2)住民生活部防災環境課
オンラインワンストップ申請の導入について(30代 町外)
内容
ふるさと納税をしましたが、オンラインでワンストップ納税ができないのはなぜですか。
対応しない理由を聞かせてください。
回答
この度は、幕別町へのご寄附を賜り、誠にありがとうございます。また、オンラインワンストップ申請の導入について、ご意見をいただきありがとうございました。
町では、寄附を通じて「みんながつながる 住まいる まくべつ」を将来像として、魅力ある街づくりを目指してきたところです。
ご質問いただきました、オンラインワンストップ特例については、令和4年中の寄附から、一部自治体において申請が開始されておりましたが、当町においてはこれまで予算措置等の検討をすすめ、この11月中旬を目途にオンラインワンストップ申請を開始するべく、準備を進めているところであります。
ご不便をお掛けし申し訳ございませんでした。今後とも、幕別町への温かい応援をいただけますと幸いです。
担当部署
経済部商工観光課
令和6年能登半島地震の義援金(募金)について(40代女性 幕別市街地)
内容
- 令和6年能登半島地震の義援金(募金)が少ない。
- 義援金を受け付けていることについて、知られていないのではないか。
- 町内・町外を問わず、もっと募金をしてもらいたい。
回答
令和6年能登半島地震の義援金(募金)のご質問について、お答えいたします。
令和6年能登半島地震災害義援金(募金)は、日本赤十字社の事業として行われています。
日本赤十字社は日本赤十字社法に定める民間の団体で、その定款で都道府県に支部を、市町村に分区を置くことを定めており、幕別町長が幕別町分区長を担っていることから、幕別町分区長としてお答えします。
令和6年能登半島地震災害義援金(募金)は、「日本赤十字社北海道支部幕別町分区」で受付し、日本赤十字社を通じて被災地の方々にお届けしています。
現在、受付を行っている「令和6年能登半島地震災害義援金」については、町広報紙、ホームページ、X(旧Twitter)やFacebookで町民の方々へ広くお知らせしているところです。
募金箱は、役場福祉課のほか、忠類総合支所、ふれあいセンター福寿、札内支所、糠内出張所に設置し、多くの方に募金の協力をいただいており、これ以外にも、各種団体等から直接日本赤十字社に送られている募金もあります。
各施設に設置している募金箱は、盗難などの事故を防ぐため毎日現金を回収し保管しているところですが、幕別町分区では、既に200万円を超える募金が集まっており、これらは被災地県(石川県、富山県、福井県、新潟県)に設置される災害義援金分配委員会を通じ被災者へ届けられています。
幕別町分区では、これからも被災地の方々の支援につながるよう、広く募金の協力について呼びかけを行ってまいります。
担当部署
日本赤十字社北海道支部幕別町分区事務局(保健福祉部福祉課)
アイヌ文化拠点空間整備の施設建設位置等について(40代男性 札内市街地)
内容
- 建設位置がハザードマップによる洪水浸水で最も危険なエリアの中にあることを知っているか。
- 浸水の脅威についてどんな対策を講じているのか。無対策な状況で事業が進んでいることを知っているか。
- 現在の建設位置のほかには検討しなかったと担当課から説明を受けたが、その他の最善策を模索すべきでは、また、町民から提案を受けていることを知っているか。
- 大きな洪水が発生すると、建築物や希少価値の高い収蔵物が汚泥まみれになるがどう考えているか。
回答
現在建設中のアイヌ文化拠点空間整備における施設の建設位置等に関して、いただいたご質問についてお答えします。
1点目のアイヌ文化拠点空間整備の建設位置がハザードマップによる洪水浸水で最も危険なエリアにあること、また、2点目の浸水の脅威に対してどのような対策を講じているか、さらに、3点目の他の建設位置を検討しなかったのか、というご質問に対してはまとめてお答えいたします。
アイヌ文化拠点空間整備事業は、アイヌの先祖が誇りを持ち、築き上げてきた伝統文化のすばらしさを多くの住民に紹介するとともに、アイヌと和人が協力して、その伝統文化を後世に伝えていくための中核的な施設を整備する事業であります。
現在、蝦夷文化考古館が所在する建設地は、かつて「チロットコタン」と呼ばれた集落があった場所で、アイヌの方々がまさに歴史の歩みを進めてきた思い入れの深い場所であり、アイヌ協会、関係団体との協議を重ねて建設地として決定した経緯があります。
蝦夷文化考古館の建物は、集落出身アイヌの吉田菊太郎氏が私財を投じて建設したもので、アイヌ自らが建設した資料館は北海道内に3件しか存在しない貴重な建築物であることから、現在地において必要な補修をし、保存していくこととしております。
しかしながら、ご質問にもありますように、建設予定地の想定最大浸水深が2.39mで、洪水浸水のリスクがあることは認識していますが、アイヌの方々の土地へのこだわりを尊重し、建築に当たっては、盛り土による地上高の嵩上げや建物開口部への止水扉設置、基礎壁を水密コンクリートで施工するなどの対策を講じることにより、最大限リスクを回避することとしました。
4点目の大きな洪水が発生すると展示物や建築物が汚泥まみれになるとのご指摘でありますが、整備する施設は考えうる洪水浸水に対する対策を講じるとともに、収蔵物についても、建物内の高い位置に収蔵するなどの対応を取るほか、万が一、洪水などの発災の危険が迫った際には、来館されている方の避難誘導や閉館措置をとり、来館者、職員の安全を図るとともに、貴重な収蔵物の保護にも万全を期す考えであります。
この度は、貴重なご意見をいただきましたことに感謝申し上げます。
担当部署
企画総務部政策推進課
途別小学校の閉校について(20代男性 札内市街地)
内容
- 途別小学校は途別公区の指定避難所となっていますが、閉校後は誰が鍵の開け閉めや避難所開設を行うのでしょうか。
- 途別小学校は農業の楽しさや食の大切さを教えてくれた学校ですが、札内南小学校と合併後も農業体験は引き継いでいただきたいと思います。町の考え方は。
- 閉校後、勉強に付いていけない子やいじめ、不登校などの問題が現れるのではないかと心配しています。そのような事態になった際の対策は。
回答
お寄せいただいたご意見に、次のとおり回答いたします。
(1)幕別町立途別小学校閉校後の鍵の開け閉め、避難所開設について
現在、幕別町立途別小学校を、途別地区の地震及び洪水の際、また、上稲志別、日新1及び日新2地区の地震の際の指定避難所として指定しています。災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、必要に応じて学校関係者または避難所担当職員が鍵を開け、避難者と協力のもと避難所の開設を行うこととしています。
今後、閉校後の校舎等の活用方法について協議されることから、活用方法が決定された後、避難所のあり方について調整する予定としています。
(2)途別小学校が行っていた農業体験について
途別地区は十勝の水田発祥の地の一つとされ、1986年に最後の水田がなくなり、それを機に米作りの記憶を未来の世代に受け継ごうと、翌87年から途別小学校でもち米の栽培を始めました。
途別小学校での稲作体験は、小規模校であったことで学校敷地内に水田を準備し、稲作農家だった地域の方と共に、「事前勉強」や「稲植え」「稲刈り」「餅つき」を地域一体となって行ってまいりました。
ご意見のありました、途別小学校で行われてきた農業体験の継承については、今後のあり方について地域の方のご意向を確認し、必要に応じて協議をしてまいりたいと考えております。
なお、町内小学校では食育推進事業に取り組んでおり、統合予定先となる札内南小学校においても、毎年、札内農業協同組合青年部の協力のもと、生産者の方と農協の職員の方から直接お話を聞く青空授業や収穫体験、農業機械見学を行うなど、食育推進事業を実施しているところであります。
(3)いじめ、不登校対策について
途別小学校は、小中一貫教育の推進をしていくなかで、現在、札内南小学校との音楽集会や児童間交流を行っており、来年度は、統合後の札内南小学校への登校を見据え、複数回の児童間交流を行うなど、学校生活での不安解消を目的とした教育活動を展開することとしております。
ご意見のありました、いじめ対策については、学校内や家庭でいじめ防止の意識を高める取組を行い、いじめの早期発見と学校内で組織的に迅速な問題解決に向けた体制を整えております。
また、不登校対策については、登校不安を解消するため、スクールカウンセラーや子どもカウンセラーによる相談体制により、一人ひとりに寄り添った対応を行っております。
今後においても、かけがえのない存在である児童一人ひとりが、元気で明るく学び、健やかに成長していくことができるよう、いじめの防止及び不登校対策を推進してまいります。
担当部署
(1)住民生活部防災環境課
(2)(3)教育委員会教育部学校教育課
ゼロカーボンシティの実現に係る電気自動車の考え方について(20代男性 札内市街地)
内容
ゼロカーボンシティの実現に係わって、町は電気自動車についてどのように考えていますか。
回答
幕別町では、令和5年度末に町全体の脱炭素に向けた取組計画である「幕別町地球温暖化対策実行計画」を策定し、その中で「2030年度に2013年度比で46%の二酸化炭素排出量を削減する」、「2050年にカーボンニュートラルを実現する」を目標と定め、令和6年度から具体的な取組を始めているところです。
2030年度の目標の達成に向けては、自家用車を含む運輸部門での二酸化炭素排出量を2013年度比で12%削減することが必要であり、削減に向けた取組の一つとして次世代自動車の導入を挙げております。
この次世代自動車とは、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル車などの大気汚染物質の排出が少ないまたは全く排出しない環境に優しい自動車をいいます。
このうち、電気自動車や燃料電池自動車は大気汚染物質を全く排出しないことから、脱炭素に向けて有効でありますが、水素を燃料とする燃料電池自動車は、その供給場所が現時点では限られていることから、本町としては、まずは電気自動車の普及を推進すべく、2030年度に町内の自動車の2%の普及を目標としております。
今回、ご指摘のあった電気自動車のデメリットについては町としても把握しているところでありますが、現在の技術の中で温室効果ガス(二酸化炭素、メタンなど)の排出削減を進める上では電気自動車の導入も必要と考えております。
しかしながら、ハイブリッド車やクリーンディーゼル車には電気自動車とは違ったメリットがあることや、合成燃料などの脱炭素に資する新技術の研究も進んでいることから、それら新技術の進展を踏まえ、電気自動車に限らず環境に優しい自動車が町内に普及してくことが「ゼロカーボンシティまくべつ」を実現する上で大切であると考えております。
担当部署
住民生活部防災環境課
幕別町内の学校におけるいじめ問題について(40代男性)
内容
- 「幕別町いじめ防止基本方針」の各学校への徹底
- いじめ問題に対する町としての具体的な対策の策定
回答
いじめは、いじめを受けた児童生徒の権利を侵害し、その心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることから、決して許されるものではないと認識しております。
国では、「いじめ防止対策推進法」に基づき、平成29年3月に、「いじめの防止等のための基本的な方針」を改定し、教育委員会といたしましても、国及び北海道の関係方針等を踏まえ、26年10月に策定した「幕別町いじめ防止基本方針」について、30年8月に改定を行ったところであります。
また、学校では、自らの学校実情に応じた「学校いじめ防止基本方針」を策定し、いじめの防止等のための対策を実効的に行うため、校長、教頭、主幹教諭、学年主任、生徒指導主事等からなる対策組織を設置し、いじめの防止、早期発見、対処するための具体的取組、さらに重大事態への対処について、適切に対応することとしています。
「学校いじめ防止基本方針」の中では、いじめの早期発見について、適正かつ迅速ないじめ対応のもと、全ての大人が連携し、児童生徒のささいな変化にも気付く力を高め、わずかな兆候であっても見逃すことなく、早い段階から積極的に実態把握に努めることになっております。
また、いじめの対処について、いじめの発見又は通報を受けた時は、その教職員は一人で抱え込まず、直ちに校長に報告し、校長はその後、速やかに「学校いじめ対策組織」により、事実確認を行い、いじめが明らかになった場合は、被害・加害児童生徒の保護者に対し報告や支援を行っていくこととなっております。
今回のお手紙にありました、当該校におけるいじめの事案につきましては、いじめに対する認識の甘さと初期段階での組織的な対応の遅れがあったと認識しており、教育委員会で報告を受けた際に、学校教育推進員から対応の指導ほか、対応の改善につきましても指導したところであります。
また、3月8日に開催した町内小中学校校長会議で全ての校長に対し、いじめに対しては、早期発見と、組織的に迅速な問題解決に向けた対応に努めるとともに、その対応の中では、保護者の心情に対する共感的な理解に努め、保護者の理解と協力を得ながら進めることにつきまして、今一度、学校内で再確認するよう指導したところであります。
さらに、「いじめ防止基本方針」について、児童生徒や教職員のほか、保護者に対しても周知を行うなど、学校内や家庭で、いじめ防止の意識を高める取組を行うよう促したところであります。
これからも、かけがえのない存在である児童生徒一人ひとりが、元気で明るく学び、健やかに成長していくことができるよう、いじめの防止等の対策を推進してまいります。
担当部署
教育委員会教育部学校教育課
(1)学童保育料について(2)自転車用ヘルメットの助成について(30代女性 札内市街地)
内容
- 自治体によって学童保育料に差があるのはなぜなのか。
- 自転車利用時のヘルメットの助成金制度の検討をお願いしたい。
(1)回答
幕別町では、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、家庭において保護者の保育を受けられないことを常態とする小学校1年生か ら6年生までの児童を保育するために学童保育所を設置しており、保育料につきましては、幕別町立学童保育所条例において月額4,500円と定めております。
ご質問の「近くの自治体で差があるのはなぜなのか。」についてでありますが、各自治体では、入所対象児童の学齢設定や保育内容等を勘案して学童保育料を定めており、十勝管内の状況を申し上げますと、無料~月額6,000円と様々で、別途おやつ代を徴する自治体もあります。
また、ご意見の中にありました芽室町の「放課後児童クラブ」につきましては、対象児童は小学校1年生から3年生までとし、学童保育料は、年間3,000円の登録料のみとなっておりますが、おやつの提供がないなど、本町における学童保育所とは事業内容が異なっております。
学童保育所では、児童に対し適切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図ることを目的に事業を実施し、事業に要する費用の一部を学童保育料として保護者に負担していただくものであり、市町村によって違いが生じていることを、ご理解いただきますようお願いします。
(2)回答
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されたところであります。ヘルメットの着用は事故発生時に被害を軽減する効果があることを認識してもらうとともに、常にヘルメットを着用する意識を醸成することが重要であります。
そのことから、令和5年7月に、幕別町生活安全推進協議会、帯広警察署と合同でヘルメット着用を呼び掛ける街頭啓発を実施したほか、各学校の交通安全教室時に自転車の安全な利用等に関する指導にあわせて、普及啓発を行っているところであります。
町といたしましては、自転車の安全な走行ルールの一つとして、ヘルメット着用の重要性について引き続き普及啓発に努めてまいりますが、現状、児童生徒のみならず全ての自転車利用者に対して購入費用の助成を行うことは、大きな費用が伴うことから難しい状況にありますことをご理解願います。
この度は、貴重なご意見ありがとうございました。
担当部署
(1)保健福祉部こども課
(2)住民生活部防災環境課、教育部学校教育課