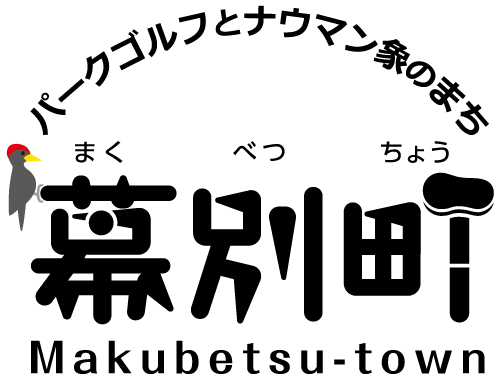アイヌ語に由来する幕別町の地名
ページID:170012740更新日2025年3月6日
アイヌ語に由来する幕別町の地名
北海道の地名はもともとアイヌ語で付けられています。のちに日本語由来の地名に置き換わった場所が多くありますが、町名をはじめ、幕別町にもアイヌ語に由来する地名が数多く残っています。現在でも、北海道各地にアイヌ語に由来する地名がたくさん残っているのは、江戸時代に和人が調査に来た時、また、明治になって本州からたくさんの移住者がやってきたり、地図を作ったりした時に、アイヌ民族の舟に乗って移動したり、案内してもらったりすることが必要だったからです。
アイヌ語で川を表すペッ《(主に流れとしての)川》やナイ《(主に地形としての)川》で終わる呼び名に由来する「…別」「…内」だけでも、幕別や猿別、札内や糠内などたくさんの地名があります。以下では、幕別町にあるアイヌ語に由来する地名をとり上げますが、アイヌ語での呼び名と変わってしまったり、指していた場所が変わってしまったり、漢字にひかれて読み方が変わってしまったりしたものがたくさんあります。また、白人(ちろっと、いまの千住)や咾別(いかんべつ、いまの相川)のように、アイヌ語の地名を無理やり漢字で表記したことによって、難読地名となっているものもあります。
| アイヌ語のよび名 | もともと指していた場所 | アイヌ語に由来する地名 | 語源など |
|---|---|---|---|
| ヤㇺワッカピラ | 猿別川下流の東岸? 明野の幕別墓地には「ヤムワッカウタリ慰霊碑」という、幕別町のウタリ(アイヌ民族)の慰霊碑があります。 | 止若(やむわっか) (今の幕別市街・明野のあたりを止若と言いました) | ヤㇺ(冷たい)ワッカ(水(が出る))ピラ(崖) 猿別川下流の東岸に湧水の出る崖があったと言われています。北海道南西部で「冷たい」はナㇺと言い、似た地名に滑若(なめわっか)があります。 |
| イカウンペッ | イカンベツ川 かつて十勝川から南に流れて旧途別川や猿別川に合流していました。 | 咾別(いかんべつ) (相川の旧字名) | イカ(近道)ウン(がそこにある)ペッ(川) イカウンペッやイカ(近道する)ペッは、蛇行している川の堤防が切れてまっすぐ行くようになった川を指します。 |
| マクンペッ(マㇰウンペッ) | どの川を指していたのか不明です。旧途別川とも、幕別市街を流れる沢とも言われています。明治~昭和初期の地図には旧途別川と猿別川が合流し、十勝川に合流するまでの川が「幕別川」となっています。 | 幕別(まくべつ) (もとは猿別市街の周辺?) | マㇰ(後背=川の流れに垂直な方向にある川岸から離れた土地)ウン(にある)ペッ(川) 幕別の読みはもともと「まくんべつ」でしたが、漢字に引かれて「まくべつ」になりました。「マカンベツ」やマㇰアンペッと呼ばれていた場所・川と同じものかは不明です。 |
| チロット~チロトー | 千住(せんじゅう)にあった沼 千住は先住民族アイヌが大勢住んでいることにちなんで名づけられました。 | 白人(ちろっと) (千住の旧字名) | チㇼ(鳥)オッ(がたくさんいる)ト(沼)。 白鳥が飛んでくる沼があったからと言われています。幕別町のアイヌの方はチㇼ(鳥)ロㇰ(が座る)ト(沼)と言うこともあります。 |
| サㇻペッ | 猿別(さるべつ)川 | 猿別(さるべつ) | サㇻ(葦)ペッ(川) 葦(アシ/ヨシ)の生える湿原があったことにちなむと考えられています。上流にある更別(さらべつ)、猿別川の支流のサラベツ川も同じ呼び名に由来するようです。 |
| サッナイ | 札内(さつない)川 | 札内(さつない) | サッ(乾く)ナイ(川)。 乾期に水がなくなる川を言います。幕別のアイヌの方はサッテキ(~ㇰ)(痩せる)ナイ(川)とも言ったようです。 |
| ペッチャㇻ | かつて十勝川が北の流れ(今の本流)と南の流れ(今のメン川)に分かれていたところ。 | 別奴(べっちゃろ) (札内の旧字名) | ペッ(川)チャㇻ(口) 川の分流点はチャㇻ(口)、川が本流や海に入るところはプッ~プトゥ(フ)(川口)と呼ばれます。 |
| メㇺ | メン川のあたり 明治時代には今のメン川は十勝川の南の流れとなっていました。 | メン川 | メㇺは「泉池」のことです。幕別のアイヌの方は「メンワッカ」(ワッカは「水」の意味)とも呼んだようです。また、十勝川とメン川の合流点で熱い湯が自噴していて、周囲のアイヌが入浴していたようです(明治31(1898)年の大洪水で噴出が止まりました)。 |
| ポロナイ | 幌内沢(幕別町葬斎場(豊岡)の沢) | 幌内沢(ほろないざわ) | ポロ(大きい)ナイ(川) ポロナイと対になるのはポン(小さい)ナイ(川)です。忠類の幌内(川)も同じ語源と思われます。 |
| イナウウㇱペッ | 稲士別(いなしべつ)川(?) ※川の名前は稲「志」別ではなく、稲「士」別となっています | 稲志別(いなしべつ) | イナウ(木幣)ウㇱ(がたくさんある)ペッ(川) 川口に祭り場があってイナウ(木幣)が立っていたのかもしれません。幕別町生まれのアイヌにイナワシと呼ぶ方もおり、イナウ(木幣)アシ(を立てる)に由来すると考えていたようです。 |
| トゥペッ(~トペッ) | 途別(とべつ)川 | 途別(とべつ) | 一般にはト(沼)ペッ(川)とされますが、幕別町出身のアイヌの方でトゥペッと呼んでいる方がいたほか、明治20, 30年代の地図ではト゜ペッ(トゥペッ)と書かれていることがあることから、トゥ(2つの)ペッ(川)とも考えられます。 |
| フㇽコ(ー)マㇷ゚、フㇽコオマペッ | 古舞(ふるまい)川 (かつてはフルコマップ川と呼ばれていました) | 古舞(ふるまい) | フㇽ(丘)カ(の上)オマ(にある)ㇷ゚(もの)/ペッ(川) 台地の上を流れる古舞川を指すと考えられます。 |
| オンネナイ | 恩根内(おんねない)川 | 恩根内(おんねない) (のちに新和になりました) | オンネ(大きい(親の))ナイ(川) オンネ(大きい(親の))と対になるのはポン(小さい(子の))です。2つのものの大きい方をオンネと言います。 |
| モアチャ | 茂発谷(もあちゃ)川 | 茂発谷(もはちや) (のちに新和になりました) | モアチャが「太蒲」とされることがありますが、モアチャにそのような意味は確認できません。「モアチャ」というところに太蒲(ガマ)が生えていたことを説明したものと思われます。幕別町生まれのアイヌでモアソロと呼ぶ方もいました。 |
| イタラタラキ | 下イタラタラキ(下似平)? 美川(みかわ)は三河(みかわ)(愛知県)の人が入植したことに由来します。 | 似平(いたいら) (下似平が美川・勢雄(せお)となりました) | イ(それ)タラタラㇰ(がデコボコな)イ(ところ)? イタラタラキの語源ははっきりと分かりませんが、現地によく見られた十勝坊主を指すと考える人もいます(『勢雄遺跡 先土器遺跡の発掘報告』『十勝アイヌ語地名手帖』)。 |
| ヌカナイ | 糠内(ぬかない)川 | 糠内(ぬかない) | ヌカン(細かい=小石の)ナイ(川)? |
| チウルイトープイ | 当縁(とうべり)川の支流 明治期の地図では現在セオトープイ川となっている川にこの名前がついています。 | 忠類(ちゅうるい) | チウ(流れ)ルイ(が激しい)トープイ(当縁(とうべり)川) |
| セイオトープイ | 当縁(とうべり)川の支流 今の上ヒチュウルイ川? この川に架かる「錦橋」には「セーオトープイ川」とあります。 | セ(ー)オトープイ川 | セイ(貝)オ(がそこにある)トープイ(当縁(とうべり)川) 昭和23(1948)年に幕別町から更別村に編入された勢雄(せお)も「セイ(貝)オ(がそこにある)」という言葉を含んでいます。 |
| チホマイワ | 丸山(チョマナイ山) | チョマナイ山 チョマナイは丸山の南麓を流れていた小川のチホマ(恐ろしい)ナイ(川)に由来すると考えられます。 | チホマ(恐ろしい)イワ(聖山) 明治27(1894)年にこの山の南麓に入植した岡田新三郎は、アイヌ民族も和人もこの山に恐怖の念を抱いていたため、「開拓」に支障が出ることを心配し、頂上に丸山神社を創建しました(現在、丸山神社は元忠類にあります)。 |
| シケㇾペウンナイ | 忠類の東宝のあたりを流れていた川や下当縁川の一部、現在のコイカクシュトープイ川の支流にも同様の名前の川がありました。 | シキリブナイなど | シケㇾペ(キハダ)ウン(がそこにある)ナイ(川) 忠類地区の古い地図や文書には、シケㇾペ(キハダ)ウン(がそこにある)ナイ(川)(明治29年陸地測量部地図)やシケㇾペ(キハダ)ウㇱ(がたくさんある)ナイ(川)(松浦武四郎『東蝦夷日誌』)という呼び名が記録されています。かつて東宝を指していた「シキリブナイ」という名前はシケㇾペ(キハダ)ナイ(川)が変化したものと考えられます。 |